

2025年02月08日
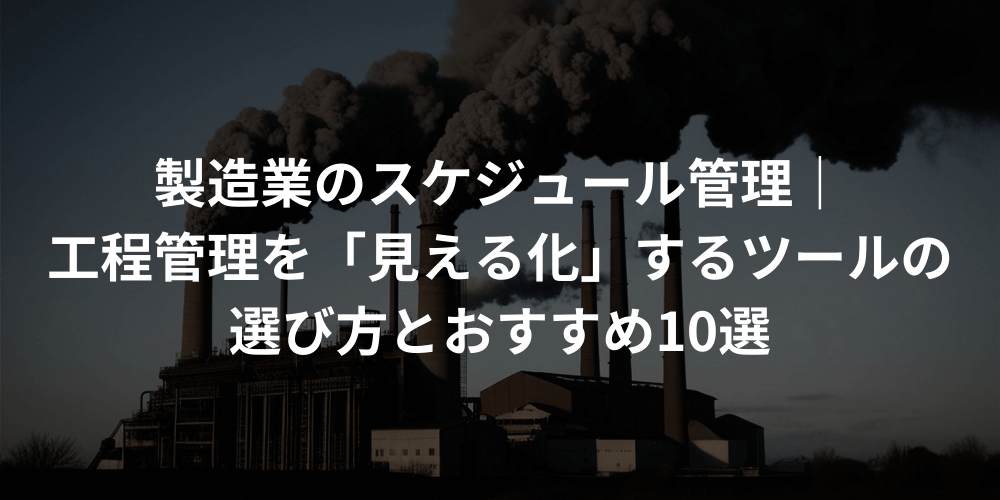
製造業で「もっと効率よく工程管理を進めたい」と感じているも多いのではないでしょうか。
多品種・少量生産や突発的なトラブル、現場との情報共有の遅れなど、行程管理に関する悩みを抱える企業は少なくありません。これらの課題を放置すると、生産性の低下やコスト増加につながり、競争力を失うリスクも考えられます。
そんな悩みを解決する鍵となるのが、製造業向けのスケジュール管理ツールです。これらのツールを活用すれば、工程の進捗をリアルタイムで把握し、無駄を削減しながら作業効率を向上させることができます。
ツールの中にも、全体工程管理に特化したツールや、IoT機器と連携してデータを活用する次世代型ツールなど、目的や現場の規模に応じて選べる多彩な選択肢があります。
さらに、データの一元管理やレポート作成を通じて、現場の作業を可視化し、長期的な業務改善にもつながります。
本記事では、製造業に特化した工程管理の基本を解説した上で、具体的なツールの特徴や選び方をわかりやすくご紹介します。
「どのツールを導入すれば現場にフィットするのか」といった疑問を解消しながら、最適なスケジュール管理を実現する方法を解説します。効率化を目指したい方はぜひ参考にしてください。

工程管理とは、製造業で製品を完成させるための作業手順や進行状況を計画・管理することを指します。その目的は、生産効率の向上、品質の安定、コスト削減を実現することです。
例えば、自動車部品の製造では、工程ごとの作業時間や順序を正確に管理することで、無駄を省きスムーズな生産が可能になります。また、工程管理を徹底することで、不良品の発生を抑え、品質を一定に保つこともできます。
さらに、進捗状況をリアルタイムで把握し、資材の発注や作業スケジュールを調整することで、過剰在庫や作業の遅れを防ぐことができます。
このように、工程管理は製造業において効率化と品質向上を実現する重要な仕組みと言えるでしょう。工程管理を理解したところで、次項では工程管理システムを活用するメリット4選を紹介します。
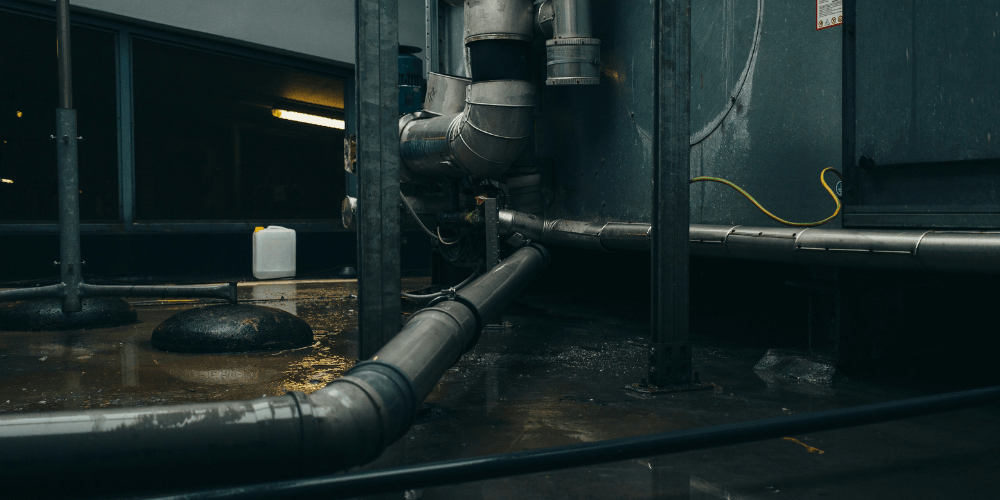
工程管理システムを活用するメリットは、以下の4つです。
それぞれ解説します。
工程管理システムのメリット1つ目は、コスト削減です。
工程管理システムを導入することで、製造業では生産にかかる無駄を削減でき、コストの最適化が実現します。特に、在庫管理や作業効率の改善に貢献します。
例えば、資材の発注をリアルタイムで確認し、必要量だけを適切なタイミングで確保することで、過剰在庫や欠品を防ぐことが可能です。
また、システムを活用することで手作業によるミスが減り、リカバリーにかかる余計なコストも抑えられます。作業の進捗が遅れている場合でも、システムが早期に警告を出すため、対策を講じやすくなります。
これにより、納期遅延を防ぎ、顧客からの信頼を保つことができます。
工程管理システムのメリット2つ目は、作業効率と生産性の向上です。
工程管理システムを導入することで、現場作業の効率化が進み、全体の生産性が向上します。このシステムは、作業スケジュールや工程の進捗をリアルタイムで把握することが可能で、計画の見直しや調整を迅速に行う手助けをします。
生産ラインで作業の遅れが発生した場合、システムが早期に通知を行い、即時に対応策を講じることができます。これにより、作業の停滞を抑えられます。
また、従来は人力で行っていた作業の進捗確認を自動化できるため、監督者の負担も軽減されます。
さらに、工程管理システムはタスクを視覚的に表示する機能を備えており、作業者全員が何をすべきか一目で理解できる環境を提供します。これにより、無駄な動きやミスが減少し、全体の作業スピードが向上します。
例えばある食品製造業では、作業指示がデジタル化されることで、製品ごとの工程が明確になり、ミスが減少しました。
工程管理システムのメリット3つ目は、データの一元管理による情報共有の効率化です。
製造現場では、データの分散が原因で情報共有が遅れ、作業の効率が低下することがあります。工程管理システムを導入することで、これらのデータを一元管理し、誰でも必要な情報に迅速にアクセスできる環境を整えることが可能です。
工程管理システムを活用すれば、製造ラインの進捗状況や必要な資材の在庫数をリアルタイムで共有できます。これにより、作業者間や部門間での情報伝達がスムーズになり、業務が効率化されます。
また、システム上でタスクの進捗を全員が確認できるため、作業の遅れや変更点がすぐに共有され、無駄なコミュニケーションが減少します。ある工程でトラブルが発生した場合、関係者全員にリアルタイムで通知されるため、迅速に対応策を協議することが可能です。
工程管理システムのメリット4つ目は、過去データの蓄積と分析による業務改善です。
工程管理システムは、製造現場の過去データを蓄積し、分析する機能を持っています。これにより、これまで見えにくかった問題点を洗い出し、具体的な改善策を導き出すことが可能です。
過去の生産スケジュールや不良品の発生率をデータとして蓄積することで、次回の生産計画をより正確に立てることができます。また、不良品の発生頻度が高い工程を特定し、その原因を分析することで、品質改善にもつながります。
さらに、データ分析によって、生産の効率が低下しやすいタイミングや、作業者の負担が集中する工程を見つけ出すことが可能です。そのため、作業の再配置や工程の見直しを行い、全体的な業務効率を向上させることができます。
ここまで、行程管理システムを導入するメリットについて見てきました。次項では製造業での工程管理システムの2つのタイプについて解説します。システムのタイプを知ることで、会社の状況に応じたツールがより選びやすくなるでしょう。

製造業で工程管理システムには、主に以下の2つのタイプに分かれます。
それぞれの特徴を解説します。
1つ目のタイプは、多品種・少量生産向けのスケジュール管理システムです。
このタイプの特徴は、製造業で多くの種類の商品を少量ずつ生産する際に最適な点です。このような生産スタイルでは、各製品の生産スケジュールが複雑になりやすく、柔軟な管理が求められます。
例えば、注文ごとにカスタマイズが必要な製品を製造する会社の場合、受注内容や納期が商品ごとに異なることがよくあります。このような状況では、各工程の進捗状況を細かく把握できるシステムが重要です。
具体的には、原材料の手配から製品の出荷までを一元的に管理できるツールが役立ちます。また、予期しないトラブルや急な仕様変更にも対応しやすい設計がされていることが多いです。
多品種・少量生産向けのシステムを導入することで、無駄な時間やコストを削減し、効率的な生産体制を構築することが可能です。たとえば、「トヨタ生産方式」のようなジャストインタイム管理を応用し、必要な時に必要な量だけを生産する仕組みを整える企業もあります。
このようなシステムを活用することで、在庫の管理が容易になり、生産計画がスムーズに進むでしょう。
2つ目のタイプは、汎用型のスケジュール管理システムです。
このタイプは、特定の製造方式に縛られず、さまざまな製造業で利用できる柔軟性が特徴です。製品の種類や生産量に関わらず、基本的な工程管理を効率化するのに適しています。
汎用型のシステムは、特定の製造スタイルに特化していないため、幅広い企業に対応できます。たとえば、製品の生産計画や進捗管理、在庫管理、納期管理など、製造業に共通する課題を解決するために設計されています。
具体的には、ガントチャートやカレンダー機能を活用し、工程ごとのスケジュールを視覚的に管理できる仕組みが一般的です。
このようなシステムを導入することで、全体の作業工程を見える化し、業務の効率化が図れます。例えば、複数のラインで同時進行している生産プロジェクトを一元管理することで、作業の重複や無駄な工程を削減することができます。
また、小規模から中規模の製造業でも、システムのスケーラビリティ(拡張性)が高いため、将来的な成長に合わせて柔軟に対応できる点が利点です。
弊社では、Googleカレンダーやホワイトボードなどの、スケジュール管理ツールを徹底比較する資料をご用意しております。
30秒ほどでダウンロード可能です。ツールごとの強みや弱みを詳しく知り、スケジュール管理を効率化したい方に向けた内容になっております。
次章では、それぞれのタイプを理解した上で、工程管理システムの選び方について見ていきましょう。

製造業で工程管理システムを導入する際の選び方は、以下の4つです。
それぞれ解説します。
製造業で工程管理システムを導入する際の選び方1つ目は、使いやすさと現場での操作性です。
システムが複雑で操作が難しいと、現場のスタッフがうまく使えず、効果が減少してしまいます。そのため、直感的に操作できる画面や、シンプルな手順で情報を入力・確認できる仕組みが重要となります。
例えば、工場の作業員がタブレットやパソコンで簡単に工程の進捗を入力できれば、リアルタイムで正確な情報が集まります。その結果、管理者は最新の状況をすぐに把握でき、生産計画の調整もスムーズに行えます。
また、専門的な知識がなくても使えるシステムであれば、新人スタッフでもすぐに操作を覚えることが可能で、教育のコストを削減できます。
製造業では多くの人が関わって作業を行うため、誰でも簡単に使えるシステムが求められます。そのため、実際に現場で働く人々の意見を取り入れて、最適なシステムを選ぶことが重要です。
製造業で工程管理システムを導入する際の選び方2つ目は、他システムとの連携性です。
生産現場では、在庫管理や販売管理など、さまざまなシステムが使われています。これらと工程管理システムがうまく連携できれば、情報の共有がスムーズになり、業務効率が向上します。
例えば、在庫管理システムと連携できる工程管理システムであれば、必要な材料の在庫状況をすぐに確認できます。これにより、材料不足による生産の遅れを防ぐことができます。
また、販売管理システムとつながっていれば、受注情報から自動的に生産計画を立てることも可能です。
このように、他のシステムと連携できるかどうかは、業務全体の流れを円滑にする上で重要なポイントです。
連携性が高いシステムを選ぶことで、データの二重入力を避け、ミスを減らすことができます。結果として、時間の節約やコストの削減にもつながります。
製造業で工程管理システムを導入する際の選び方3つ目は、進捗管理・共有以外の機能の要否です。
基本的な進捗管理や情報共有に加えて、さらに便利な機能が必要かどうかを考えることが重要です。必要な機能を明確にすることで、自社に最適なシステムを選ぶことができます。
品質管理の機能があれば、製品の品質をチェックし、不良品を減らすことができます。また、設備のメンテナンス情報を管理できる機能があれば、機械の故障を予防し、生産の停止を防ぐことができます。
さらに、データ分析の機能があれば、生産効率を上げるための改善点を見つけることができます。
このように、進捗管理以外の機能が充実しているシステムを選ぶことで、業務の幅を広げることができます。ただし、多機能なシステムは操作が複雑になることもあるため、本当に必要な機能だけを選ぶことが重要です。
製造業で工程管理システムを導入する際の選び方4つ目は、導入実績と業界での評価です。
多くの企業で使われているシステムや、業界で高く評価されているシステムは、信頼性が高いと言えます。そのため、安心して導入を検討することができます。
例えば、同じ業種や規模の企業で導入されているシステムは、自社でも効果を発揮しやすいでしょう。また、専門の雑誌やウェブサイトで高い評価を受けているシステムは、機能やサポート体制が充実している可能性が高いです。
このように、導入実績や評価を参考にすることで、失敗のリスクを減らすことができます。さらに、実際にそのシステムを使っている企業の声を聞くことができれば、より具体的なイメージを持つことができます。
導入後のサポートやトラブル対応なども確認しておくと、安心して使い始めることができるでしょう。
次項では、先ほど紹介した2つのタイプ別に、おすすめのスケジュール管理ツールを10つ紹介します。

製造業・工程管理におすすめのスケジュール管理ツールを先ほど解説した2つのタイプ別に紹介します。
多品種・少量生産向けのスケジュール管理ツールは、以下の5つです。
それぞれ解説します。

画像引用:https://smartf-nexta.com/
1つ目のツールは、スマートFです。
スマートFは、多品種・少量生産向けの工程管理に特化したスケジュール管理ツールで、現場の負担を軽減しながら効率的な作業を実現できるツールです。
このツールの特徴は、直感的に操作できる画面設計と、多品種生産に対応した柔軟なスケジュール調整機能です。
例えば、個々の商品ごとに異なる納期が設定されている場合、スマートFを使えば、それぞれの工程を細かく分けてスケジュール化できます。
また、変更が発生した際にもドラッグ操作で簡単に修正できるため、トラブルへの対応もスムーズです。進捗状況をリアルタイムで確認できるため、管理者が全体の状況を把握しやすくなります。
導入企業の事例として、受注生産を行う中小規模の製造業では、スマートFを使うことで、手作業によるスケジュール管理からデジタル化を進め、作業効率を改善したという声が寄せられています。
現場の実情に即した機能を備えており、多くの製造業で活用が期待されています。
公式サイト:https://smartf-nexta.com/

画像引用:https://monorevo.jp/
2つ目のツールは、ものレボです。
このツールは、多品種・少量生産の複雑な工程を見える化し、管理者が迅速に意思決定できるよう支援することを目的としています。特徴的なのは、AIを活用した生産スケジュールの最適化機能が搭載されている点です。
例えば、受注が集中した場合、どの工程にどれだけ負荷がかかるかをシミュレーションできるため、計画段階で無駄を減らすことができます。
また、製品ごとに異なる生産条件を一括管理することで、手動での調整作業を削減できます。このような機能により、工程の抜け漏れやダブルブッキングといった問題を防ぎやすくなります。
ものレボを導入した企業では、工程管理の効率化に加え、納期遅延のリスクが減少し、顧客満足度の向上にもつながったとの報告があります。
公式サイト:https://monorevo.jp/
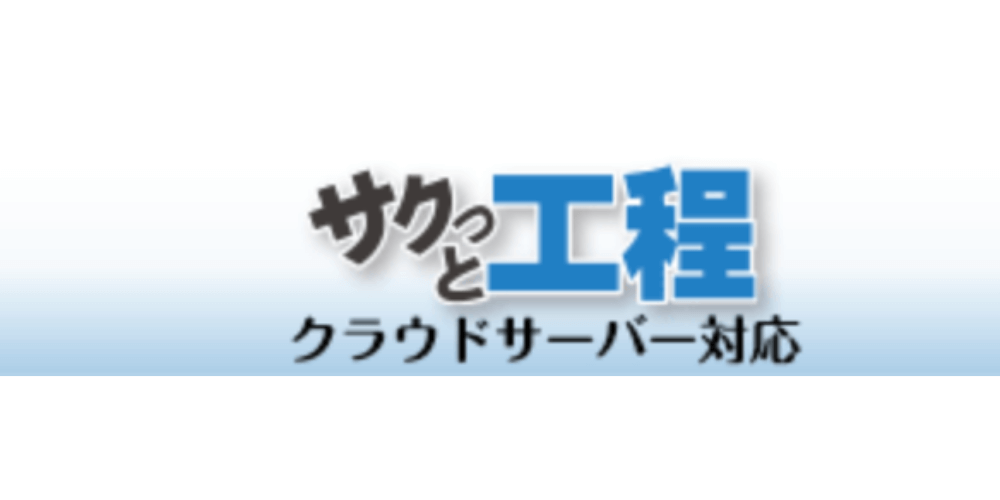
画像引用:https://www.smart-go.net/sk/
3つ目のツールは、サクっと工程です。
このツールは、名前の通り、簡単かつ迅速に工程管理を始められることを目的として開発されています。特に、多品種・少量生産でスピーディーな対応が求められる現場に適していると言えます。
サクっと工程の特徴は、シンプルな機能構成と高い操作性にあります。例えば、各工程の作業内容や担当者を簡単に入力し、カレンダー形式で進捗を確認できる機能が備わっています。
また、急なスケジュール変更が発生した場合でも、数クリックで修正が可能で、現場の混乱を抑えられます。
導入事例として、試作品を多く手掛ける企業では、サクっと工程を活用することで、進捗管理が簡単になったという声があります。
多機能ではありませんが、必要な機能に絞られており無駄な機能がないため、初めて工程管理ツールを導入する企業にもおすすめです。
公式サイト:https://www.smart-go.net/sk/

画像引用:https://www.cim.co.jp/dr-kouteinavi/
4つ目のツールは、Dr.工程Naviです。
このツールは、工程の進捗を「診断」するように見える化し、問題点を明らかにするサポートを行います。そのため、効率的な生産管理を行いたい企業に最適です。
特徴的なのは、工程の進捗状況を自動で分析し、予想される遅延やボトルネックを視覚的に示してくれる点です。例えば、特定の工程が遅れている場合、アラートが表示されるため、管理者が早めに対策を講じることができます。
また、クラウド型のシステムであるため、場所を問わずどこからでも状況を確認できるのも利点です。
Dr.工程Naviを導入した企業では、従来は手作業で行っていた工程管理を自動化することで、業務負担が軽減されたと報告されています。
このツールは細かい分析機能も備えており、より効率的な生産体制を構築するための改善提案を受けることも可能です。
公式サイト:https://www.cim.co.jp/dr-kouteinavi/

画像引用:https://www.gen-square.com/
5つ目のツールは、GENです。
GENは、多品種・少量生産向けのスケジュール管理ツールで、柔軟なカスタマイズが可能な点が特徴です。このツールを使うことで、自社の生産形態に合わせた工程管理ができ、効率的な運営が期待できます。
例えば、季節商品を扱うアパレルメーカーでは、商品の入れ替わりが激しく、工程管理が難しいことが多いです。GENは、そんな現場でも自在にスケジュールを組むことができ、急な変更にも対応しやすいです。
また、他のシステムとの連携性も高く、在庫管理や販売管理と一体化した運用が可能です。
操作性にも優れており、小学生でも理解できるシンプルな画面設計になっています。スタッフ全員が使いやすいツールを求める企業にとって、GENは強い味方となるでしょう。
生産効率を上げたい、多品種・少量生産の現場で活躍するツールです。
公式サイト:https://www.gen-square.com/
汎用型のスケジュール管理ツールは、以下の5つです。
それぞれ解説します。

画像引用:https://lychee.techmatrix.jp/
6つ目のツールは、Lychee Redmineです。
Lychee Redmineは、製造業のスケジュール管理に役立つ汎用型のツールで、プロジェクト管理を効率的に行えます。工程の進捗やタスクの状況を簡単に把握でき、チーム全体で情報を共有できます。
例えば、大きな工場で複数のプロジェクトが同時に進行している場合、誰がどの作業をしているのか分かりにくくなることがあります。
Lychee Redmineを使えば、各プロジェクトの進行状況や担当者を一目で確認できるため、全体の管理がしやすいと言えます。また、問題が発生したときも、すぐに対応策を考えることができます。
Lychee Redmineは、多くの企業で導入されており、その信頼性と使いやすさから製造業のスケジュール管理に適したツールとして評価されています。
公式サイト:https://lychee-redmine.jp/

画像引用:https://www.finereport.com/jp/
7つ目のツールは、FineReportです。
FineReportは、製造業のスケジュール管理を支援する汎用型のツールで、データの見える化に優れています。複雑な情報も分かりやすいグラフや表にして表示でき、現場の状況を一目で把握できます。
工場でたくさんの製品を作っていると、どの商品がどれくらい進んでいるのか分かりにくくなることがあります。
FineReportを使えば、各製品の進捗状況や在庫数をグラフで見ることができるため、次に何をすべきか判断しやすいと言えます。また、問題が起きたときも、その原因をデータから見つけることができます。
画面も見やすく、ドラッグ&ドロップでレポートを作成できるので、比較的簡単に使えるでしょう。現場のスタッフ全員がデータを活用し、生産性の向上につなげることができます。
公式サイト:https://www.finereport.com/jp/

画像引用:https://www.techs-s.com/product/seiryu
8つ目のツールは、Seiryuです。
Seiryuは、製造業のスケジュール管理をサポートする汎用型のシステムで、シンプルな操作性が特徴です。工程の進捗や作業予定を簡単に管理でき、現場の効率化に役立ちます。
例えば、中小規模の工場では、手作業でスケジュールを管理していることが多く、ミスが起きやすいと言えます。Seiryuを使えば、パソコンやタブレットでスケジュールを入力・確認できるため、誰でも簡単に使えます。また、情報が自動で更新されるので、最新の状況をすぐに把握できます。
このツールは、画面が見やすく、専門的な用語も少ないため、小学生でも理解できます。これにより、現場のスタッフ全員が同じ情報を共有でき、生産のムダを減らすことができます。さらに、カスタマイズも可能なので、自社のニーズに合わせて使いやすく設定できます。
Seiryuは、使いやすさとシンプルさを求める製造業のスケジュール管理に最適なツールとして、多くの企業で活用されています。
公式サイト:https://www.techs-s.com/product/seiryu

画像引用:https://www.morix.co.jp/product/workgear-x.html
9つ目のツールは、WorkGearです。
このツールは、汎用型のスケジュール管理ツールとして利用されています。特に、複数のラインや工程を一元管理したい企業に適していると言えます。
WorkGearは、リアルタイムで進捗状況を確認できる機能を備えており、現場の状況を常に把握することが可能です。
例えば、自動車部品の製造工場では、多くのラインが同時に稼働しており、各ラインの状況をタイムリーに確認することが重要です。WorkGearを導入することで、これらを効率的に管理できます。
また、WorkGearは、操作性が高く、スタッフ全員が簡単に使いこなせるほど簡単な操作性が魅力です。トラブルが発生した場合も、迅速に対応するための情報がすぐに手に入るため、生産性の低下を防ぐことができます。
公式サイト:https://www.morix.co.jp/product/workgear-x.html

画像引用:https://www.rumix.co.jp/pc/
10つ目のツールは、Project Canvasです。
Project Canvasは、製造業におけるプロジェクト型の工程管理に適した汎用型ツールで、細かいスケジュール管理が求められる現場で活躍します。
このツールは、タスクの依存関係を視覚的に整理できるため、複雑な工程も分かりやすく表示できます。
例えば、化学製品を製造する企業では、工程の順番や進捗が他の作業に影響を及ぼします。Project Canvasを使うことで、これらを最適化し、無駄を削減できます。
また、Project Canvasは、操作画面がシンプルで直感的に使えるため、特別な知識がなくてもすぐに導入が可能です。
さらに、工程管理だけでなく、予算管理や資源配分の最適化にも役立つため、総合的な業務効率化が期待されます。
公式サイト:https://www.rumix.co.jp/pc/

本記事では、製造業における工程管理の重要性やメリット、さらにスケジュール管理ツールのタイプや選び方について詳しく解説しました。
特に、「多品種・少量生産向け」と「汎用型」の2タイプに分かれるため、どちらに該当するかを理解した上でツールを選ぶことが重要です。
本記事で紹介したスケジュール管理ツールを活用し、工程管理を効率化することで、生産性の向上や業務の最適化を実現しましょう。

スケジュール管理ツールをデジタル化したいけど、スマホやパソコンが苦手なスタッフが多く、浸透するか不安といった悩みはありませんか?
そのようなお悩みは、弊社のスケジュール管理サービス「サポスケ」が解決できるかもしれません。
こちらよりサポスケの活用イメージをまとめた資料を無料でダウンロードできます。興味のある方はお気軽に試してみてください。
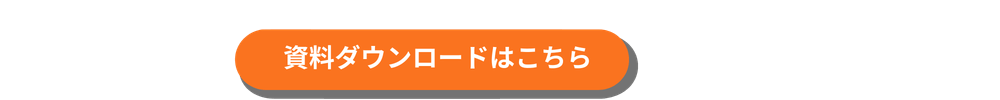
サポスケの特徴
・顧客や案件とスケジュールを紐付けて管理できて、情報を探しやすく
・入力項目は自由に設定できるから、現場に合わせた表示が可能
・アラート機能で、シフト作成時のミスを減らせる
サポスケについて、実際の画面を確認しながら更に詳細を知ることができます。
是非お気軽に資料をダウンロードしてください。